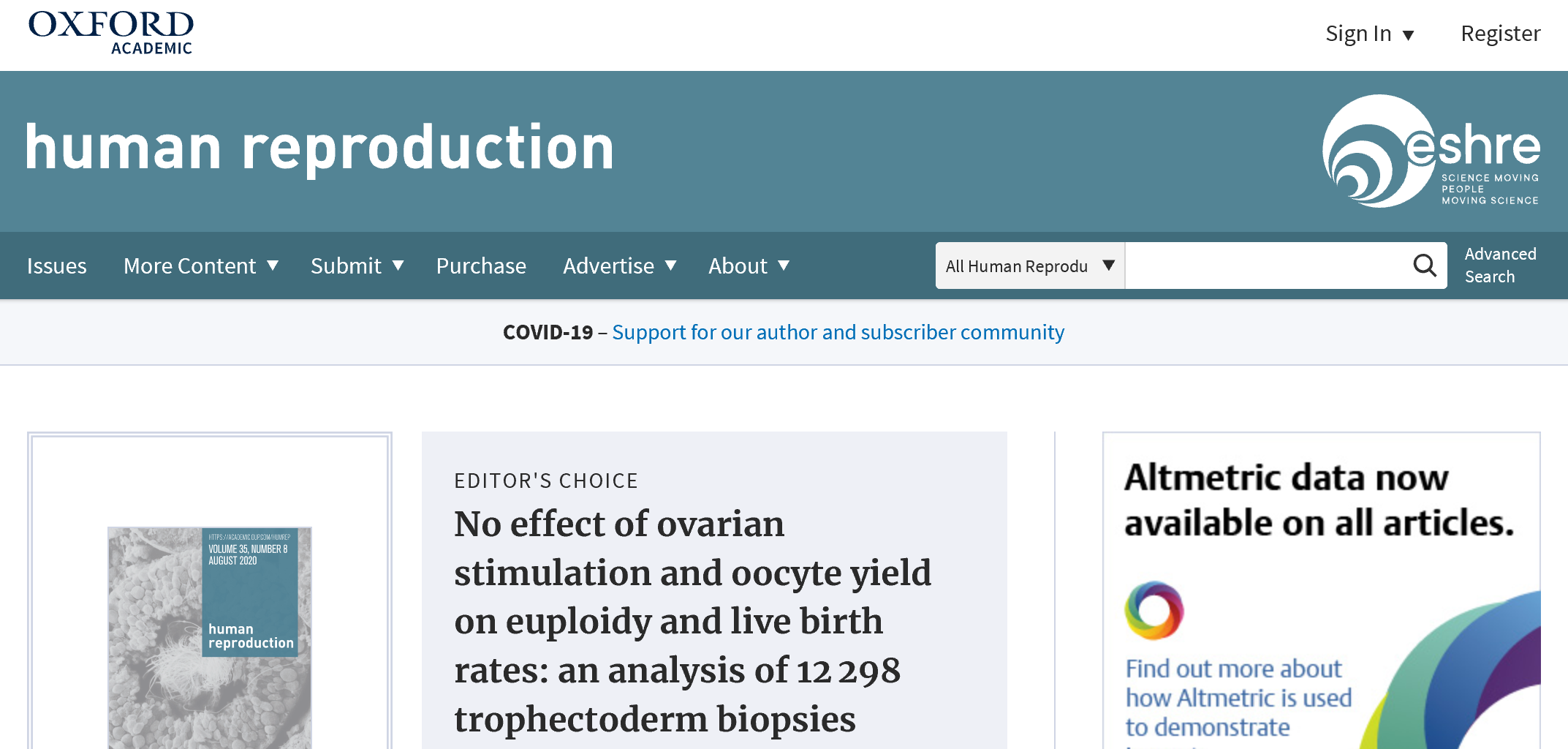新着ニュース30件
2020年9月5日 14:00
出生確率と着床前染色体検査
ボストン公衆衛生大学院、ベス・イスラエル・メディカルセンター(米ニューヨーク市の病院)、ボストンIVFセンター(全米最大の不妊治療機関)の研究チームは、「Human Reproduction」にて、35歳以上かつ自己凍結胚を用いた体外受精を受ける女性は、着床前(受精卵)染色体検査(PGT-A)の実施により出生確率が高まると発表した。今回、35歳以上の女性が体外受精を受ける場合、出生確率と着床前染色体検査に関連性があると認められた。35歳以上の女性にとって、体外受精の出生可能性を高めるうえで着床前染色体検査は有益であるという。
着床前染色体検査が体外受精の出生率に対して与える影響
研究チームは、自己凍結胚を用いた体外受精を受ける女性8227人を対象に、後向きコホート研究を実施し、着床前染色体検査が体外受精の出生率に対して与える影響を検証した。今回の調査では、1回目に回収された卵母細胞の不妊治療サイクルを評価した。被験者は、2011年1月1日から2017年10月31日の間に1回目の卵母細胞回収を行い、受精には自己の胚を用いた。
また、着床前染色体検査では、ステージ3(受精後4~5日)からステージ6(受精後約17日)、内細胞塊および外細胞塊のグレードA・B評価の良質胚のみを検査した。
調査を通して、着床前染色体検査を受けた胚は、検査未実施の胚と比べ、胚移植の成功率は顕著に低下したものの、妊娠・出生率は向上した。
着床前染色体検査の受けた女性のうち、38歳以上の出生率は35歳から37歳の女性より高く、67%と報告された。35歳から37歳の女性で着床前染色体検査を受けた場合、出生率、着床前染色体検査を実施していない女性と比べ、高くなった。
一方、35歳未満では、着床前染色体検査を実施した女性、着床前染色体検査を実施しなかった女性の出生率に相違は認められなかった。
今回は、1回目に回収された卵母細胞に限定した出生率の評価であり、複数回に亘って回収された卵母細胞を用いたサイクルにおける累積出生率は評価されていない。しかしながら、35歳以上の女性にとって、体外受精の出生可能性を高めるうえで着床前染色体検査は有益であると考えられる。
(画像はHuman Reproductionより)
Human Reproduction
https://academic.oup.com/
-->