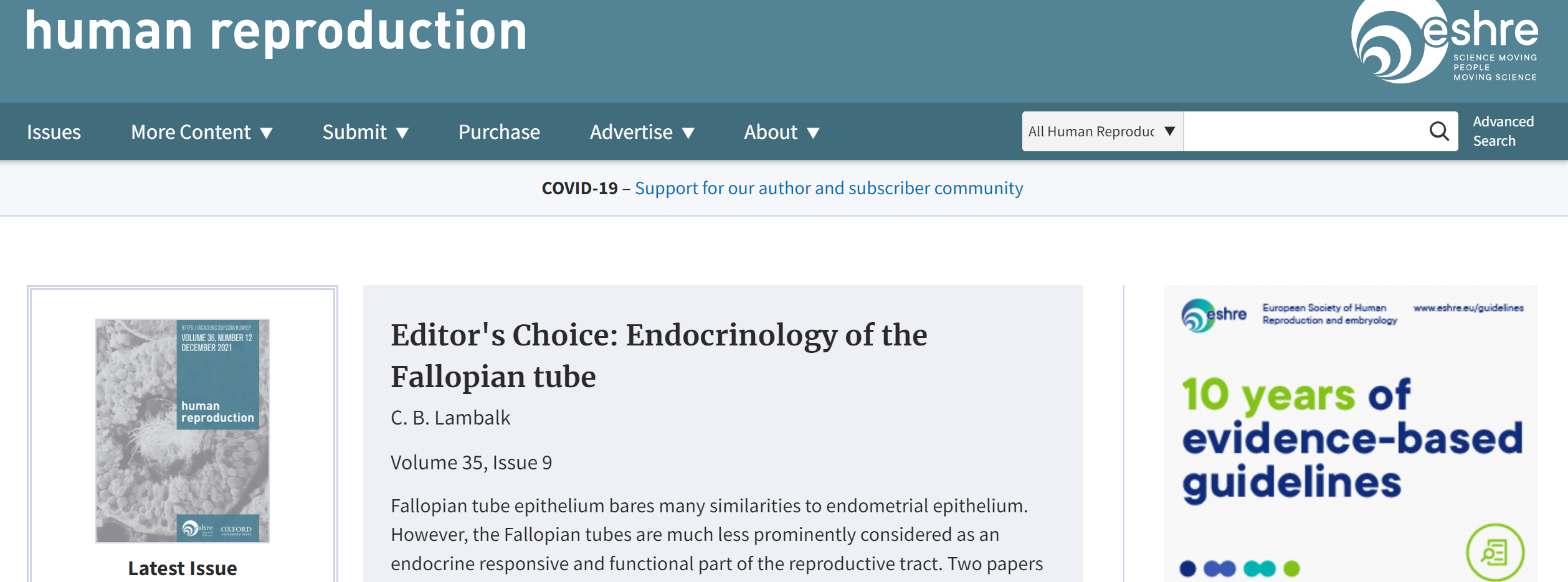新着ニュース30件
2021年12月7日 00:00
卵巣刺激なしの体外成熟培養の出生率
11月28日、中国の研究チームは、「Human Reproduction」にて、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の凍結融解胚移植において、卵巣刺激なしの体外成熟培養の出生率は、卵巣刺激ありの体外受精より下がると発表した。6ヶ月間における凍結融解胚移植の出生率を比較したところ、卵巣刺激なしの体外成熟培養1サイクル目は、卵巣刺激ありの体外受精1サイクル目と比べて出生率が低くなった報告された。ただし、卵巣を刺激しないため、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)リスクはないという。
PCOSの新たな代替不妊治療
未成熟卵の体外成熟培養(IVM)とは、成長過程の卵子を体外で成熟させる方法である。通常、体外受精や顕微授精は成熟卵を用いて行うが、なかには、未成熟卵しか採取できないケースもある。その場合、体外成熟培養によって採取した未成熟卵を体外で成熟卵まで培養させる。なお、体外成熟培養では、少量のゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)あるいは未使用で済む。そのため、PCOSの新たな代替不妊治療といわれる。
卵巣刺激なしの体外成熟培養と卵巣刺激ありの体外受精の出生率
研究チームは、2018年3月から 2019年7月の期間、不妊治療を受けるPCOSの女性351人(20~38歳、凍結融解胚移植1サイクル目)を対象に、卵巣刺激なしの体外成熟培養と卵巣刺激ありの体外受精を行い、出生率を比較した。体外受精における6ヶ月以内の妊娠率は、体外成熟培養と比べて高くなった。しかしながら、体外受精では卵巣を刺激して排卵を誘発するため、中等度から重度の卵巣過剰刺激症候群リスクが増し、176人中11人に中等度から重度の症状が認められた。
一方、卵巣刺激を行わない体外成熟培養では凍結融解胚移植による出生率は下がったが、卵巣過剰刺激症候群リスクはなかったという。
(画像はHuman Reproductionより)
Human Reproduction
https://academic.oup.com/
-->