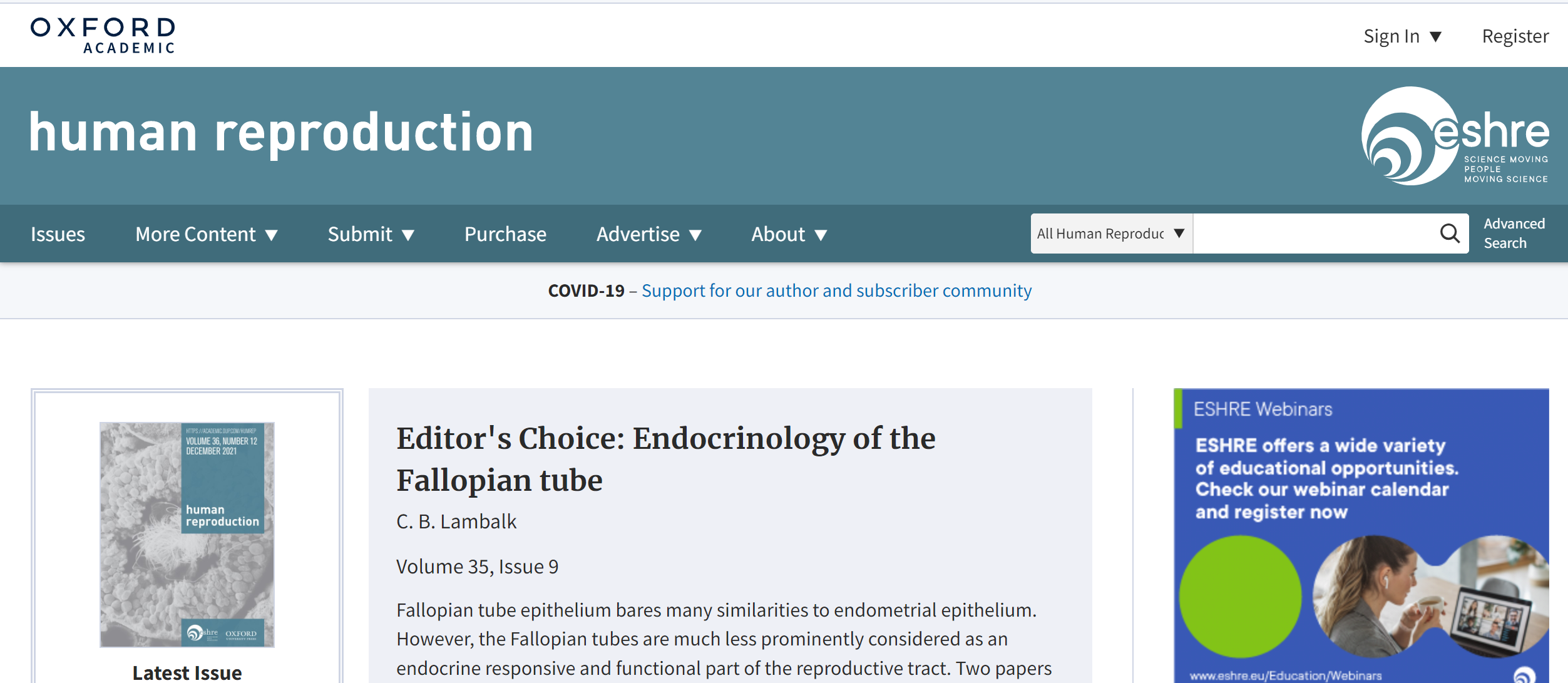新着ニュース30件
2021年11月27日 23:00
胚盤胞の発育状態が与える影響
11月19日、オールボー大学、コペンハーゲン大学などデンマークの研究チームは、「Human Reproduction」にて、胚盤胞の発育状態および形態、胎児の性別において、有意な関係性が認められたと発表した。つまり、胚盤胞の形態学的評価は、胎児の性別と関連性がある。一方、早産、出生体重との関係性はなく、影響を与えないと報告された。
胚盤胞の形態学的評価と不妊治療結果における関係性
研究チームは、2014年から2018年の期間、16の医療機関にて新鮮胚移植および凍結融解胚移植を受ける女性7246人を対象に、胚盤胞の形態学的評価(胚移植日、発達状態、栄養外胚葉、内部細胞塊)と不妊治療結果における関係性を検証した。なお、「the Danish Medical Birth Registry」によると、被験者のうち4842人が出産に至ったという。
被験者は、排卵後5日目から6日目胚盤胞を移植し、グレードはクラス1からクラス5であった。胚盤胞は、成長スピード(胚盤胞の広がり)を目安に発育状態が6段階で評価される。胚盤胞になったばかりの状態はクラス1に分類され、最も発育が進んでいる状態がクラス6となる。
また、栄養外胚葉(TE:胎盤になる部分)と内部細胞塊(ICM:胎児になる部分)の質は、3つのグレード(A:密で細胞数が多い、B:疎で細胞数が少ない、C:細胞数が非常に少ない)にて評価する。
今回、胚移植した胚盤胞のクラスは胎児の性別と関連性があった。クラス5の胚盤胞を移植した場合、クラス3と比べて男の子になる可能性が増した。栄養外胚葉のグレードより比較すると、グレードBでは、グレードAより男の子になる可能性が低下した。
一方、栄養外胚葉がグレードA、グレードCの場合、出生身長に影響を与えることが認められたが、胚盤胞の形態学的評価は、早産および出生体重と有意な関係性はなかったという。
(画像はHuman Reproductionより)
Human Reproduction
https://academic.oup.com/
-->