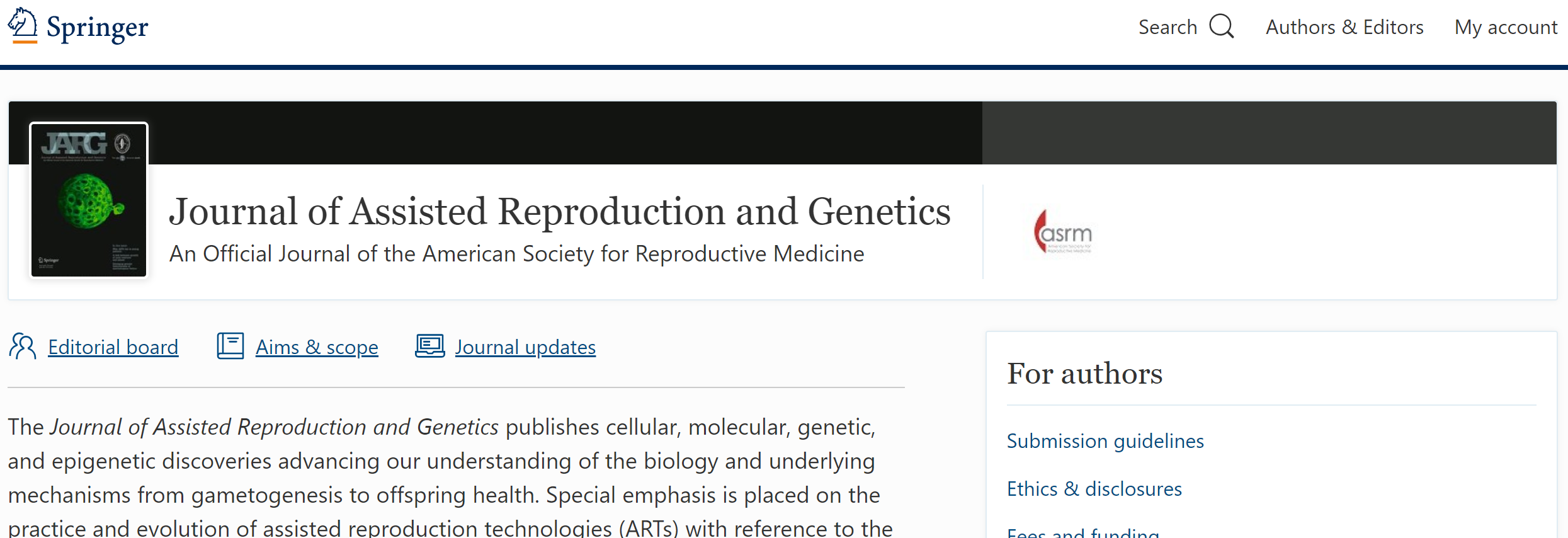新着ニュース30件
2021年8月2日 23:00
凍結融解胚移植における条件
7月26日、アメリカの研究チームは、「Journal of Assisted Reproduction and Genetics」にて、凍結融解後の胚の生存には胞状卵胞数、体外受精サイクル時期、胚盤胞のグレードが大きく影響すると発表した。凍結融解後の胚の生存に対して関与する臨床的要因
現在、生殖補助医療において、胚の凍結保存は、ガラス化法にて行われている。今回、研究チームは、体外受精を行う女性6167人を対象に、受精卵着床前検査(PGT-A)を行った胚盤胞をガラス化凍結し、凍結融解後の胚の生存に対して関与する臨床的要因を考察した。
なお、PGT-Aでは、胚移植に伴い、体外受精による胚の染色体数を検査する。これまで、不妊治療において、体外受精で得られた胚のうち、正倍数性胚(染色体数が正常な胚)を子宮に戻すことにより、妊娠・出生率が向上すると考えられてきた。
正倍数性の胚盤胞をガラス化凍結保存した場合、融解後に生存した胚は、融解に失敗した胚と比べ、体外受精サイクルにて起こるLHサージ(黄体形成ホルモン(LHホルモン)の分泌量が急上昇する現象)において、顕著にエストラジオール分泌量が高くなった。
あわせて、採取された卵母細胞の数、胞状卵胞の数も多くなった。
また、2015年以前の体外受精サイクルでは、凍結融解後の胚盤胞(5日目、6日目、7日目)の生存率が低くなった。生存した胚盤胞における内部細胞塊(胎児になる部分)の状態はグレードCとなり、体外受精には適さなかった。
これより、臨床的要因として、胞状卵胞数、体外受精サイクル時期、胚盤胞のグレードが大きく影響すると考えられる。
(画像はJournal of Assisted Reproduction and Geneticsより)
Springer Link
https://link.springer.com/
-->