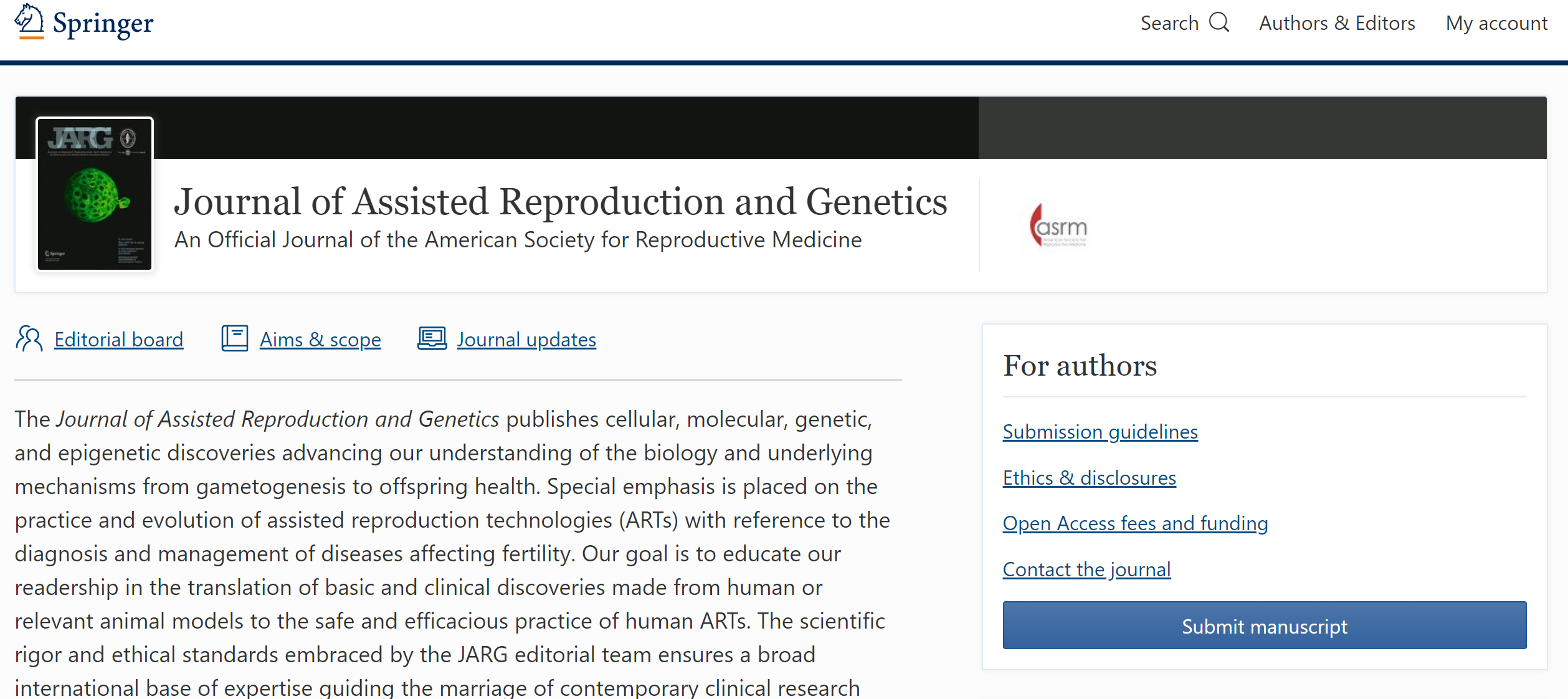新着ニュース30件
2022年2月7日 15:00
体外受精における重要な情報
2月4日、インドの研究チームは、「Journal of Assisted Reproduction and Genetics」にて、着床前診断(PGT-A)によって染色体数的異常の頻度、最も起こりやすい染色体異常が特定され、体外受精における重要な情報がもたらされると発表した。ヒト胚における染色体数的異常の発生率および性質
着床前診断(PGT-A)では、体外受精によって得られた5日目以降の胚盤胞に対して、染色体の数的異常を検査する。今回、研究チームは、2016年から2020年の期間、単一医療機関の不妊治療患者488人(胚1501個、体外受精サイクル533回、PGT-A検査あり)を対象に、後向きコホート研究(レトロスペクティブスタディ:疾病の要因と発症の関連を調べるための観察的研究の手法)を実施した。
調査対象の胚に対して、次世代シーケンシング(NGS)に用いたPGT-A検査を行い、染色体数的異常の頻度、最も影響を受ける染色体、母体年齢と異数性率における関係性、部分異数性の発生率を調査したところ、染色体数的異常の頻度は46.8%であった。
30歳以下の女性における異数性率は28%までだったが、一方、40歳以上の女性では67%まで着実に増加した。
また、染色体数的異常の高頻度は、16番、22番、21番、25番染色体に認められた。部分異数性の発生率は5.3%であり、9番染色体の長腕(9q)に最も確認されたという。
研究チームは、体外受精における染色体数的異常の頻度、最も起こりやすい染色体異常は重要な情報になると強調する。
(画像はSpringer Linkより)
Springer Link
https://link.springer.com/
-->