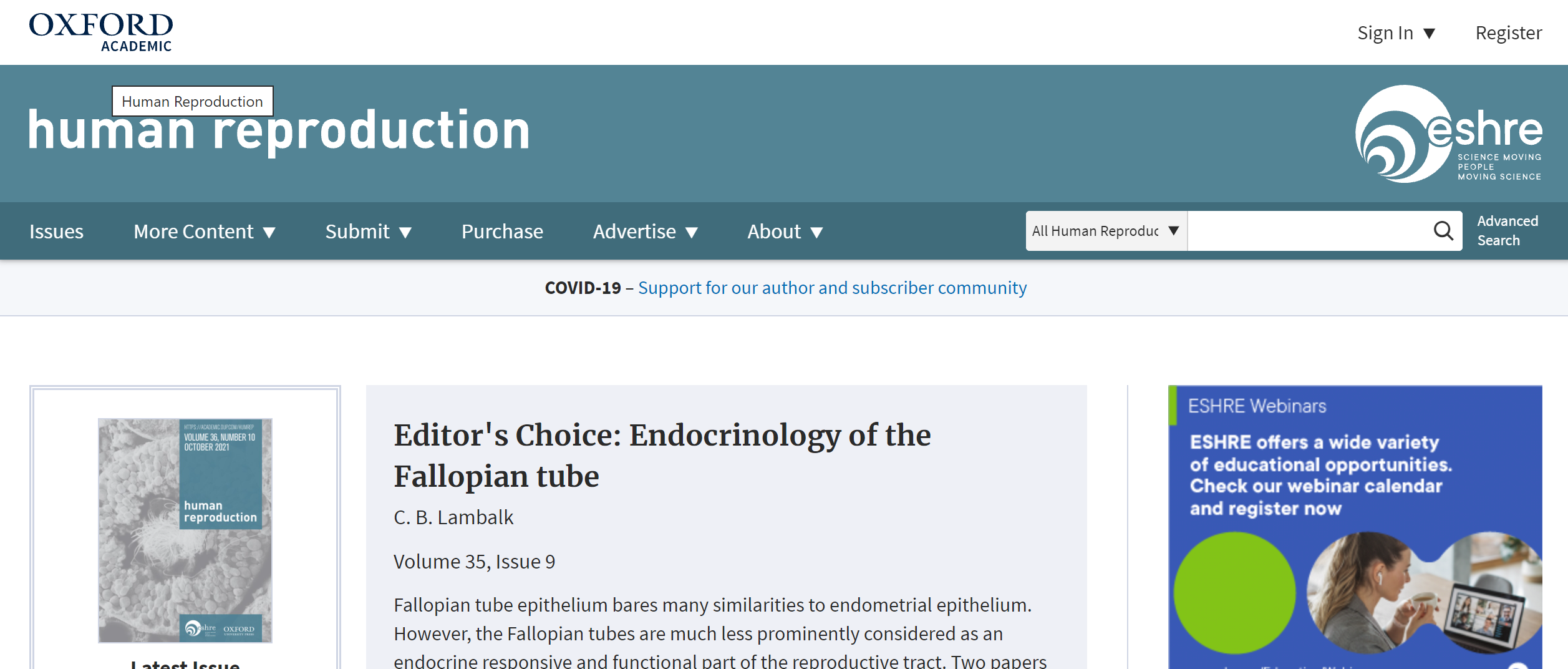新着ニュース30件
2021年10月6日 14:00
肥満が胚形成に与える影響
10月3日、スペインの研究チームは、「Human Reproduction」にて、体外受精において、肥満の女性と普通体重(標準)の女性において、卵割パターン(受精卵の細胞分裂パターン)および胚盤胞形成率に大きな相違は認められないと発表した。女性の体重が受精卵の形成過程、体外受精結果に対して悪影響を与える可能性は低いという。
女性の体重と体外受精結果における関係性
これまで、肥満は体外受精結果に悪影響を及ぼすと考えられてきた。しかしながら、一方で、肥満と卵母細胞の形成異常、受精卵の質や子宮内膜着床能(ERA)の低下における因果関係は不明であった。今回、研究チームは、2016年1月から2020年5月の期間、顕微授精を受けた女性2822人(胚17848個、顕微授精サイクル3316回)を対象に、女性の体重と体外受精結果における関係性を検証した。
なお、顕微授精には5日目あるいは6日目の胚が用いられ、着床前診断(PGT-A)実施サイクル数は1251回であった。
「低体重」「普通体重」「肥満1」「肥満2」に分類してグループごとに比較したところ、いずれも胚盤胞の形成過程は類似しており、卵割パターン(受精卵の細胞分裂パターン)および胚盤胞形成率に大きな相違は認められないという。
研究チームは、肥満女性における体外受精の失敗は、子宮内膜着床能が大きく影響していると考える。そこで、体外受精の結果を予測するうえでBMIのみをパラメーターとして用いることは適さないと指摘する。
(画像はHuman Reproductionより)
Human Reproduction
https://academic.oup.com/
-->