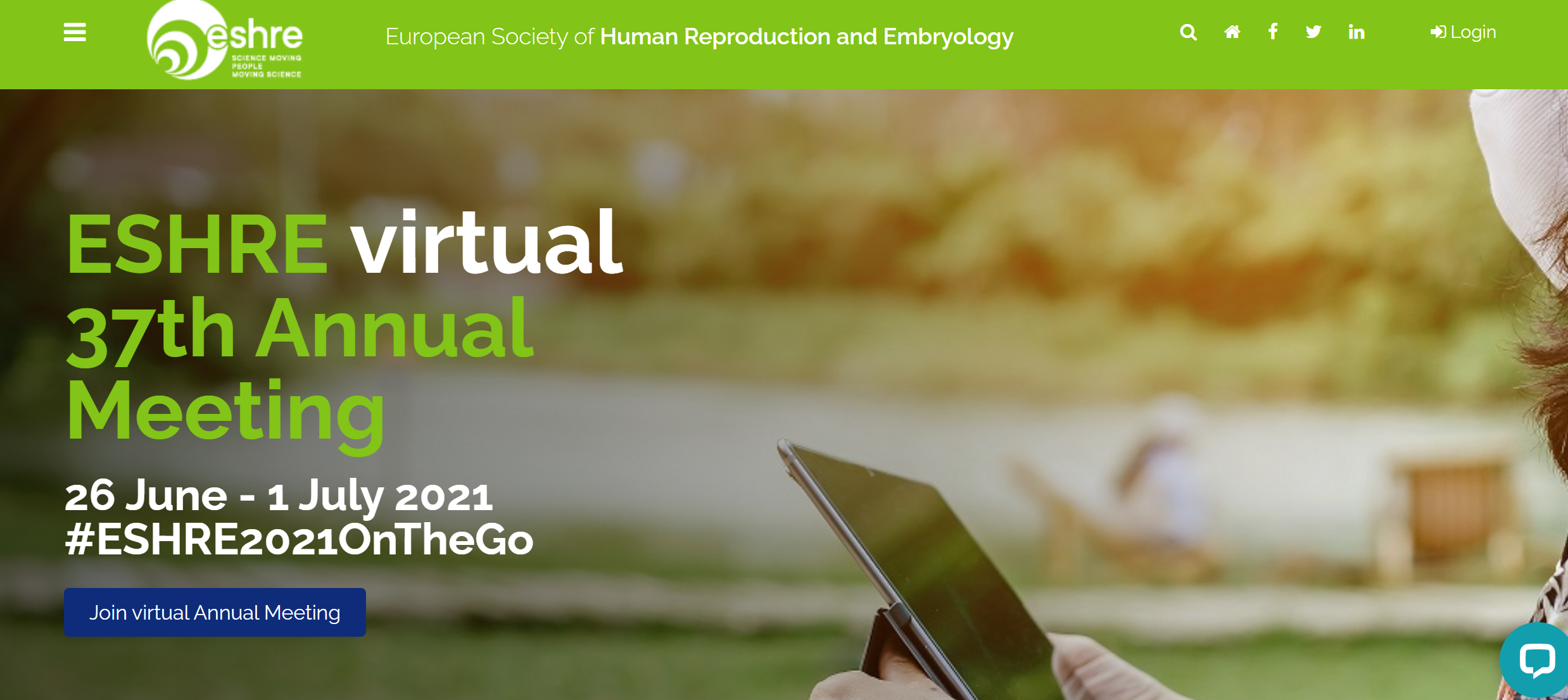新着ニュース30件
2021年7月5日 23:00
体外受精における凍結融解胚移植に伴うリスク
フランス・パリ公立病院連合Bichat-Claude-Bernard病院のシルヴィー・イーペルボイン(Sylvie Epelboin)医師が率いる研究チームは、「ESHRE2021」オンライン会議にて、体外受精において凍結融解胚移植を選択する場合、子癇前症や妊娠高血圧症候群リスクが増加すると発表した。増加傾向にある胚の凍結保存
近年、体外受精において、胚の凍結保存は増加傾向にある。凍結融解胚移植は成功率が高く、採卵に伴う卵巣の過剰刺激を軽減できるといわれる。研究チームは、フランス国家データベースを用いて、体外受精と顕微授精によって妊娠した女性のデータを分析したところ、体外受精における凍結融解胚移植と子癇前症や妊娠高血圧症リスクには関連性があることが認められた。
人工周期(ホルモン補充療法)の凍結融解胚移植では、自然周期・排卵周期(2.3%)や新鮮胚移植(2.4%)に比べて子癇前症の発症率が高く、5.3%となった。あわせて、妊娠高血圧症候群の発症率においても、凍結融解胚移植に伴う増加が確認された。
通常、黄体ホルモン(プロゲステロン)は、妊娠初期に卵巣内で形成される細胞集合を発達させる。黄体ホルモンが分泌することによって、妊娠中、子宮内膜の発達、血流の改善を促す。
一方、ホルモン補充療法は、胚移植に備えて子宮環境を整える目的で行われ、排卵や黄体ホルモン生成を抑制させる。それゆえ、凍結融解胚移植におけるホルモン補充療法は、黄体ホルモン(プロゲステロン)機能を妨げるため、妊娠合併症リスクを高めるということだ。
(画像はESHREより)
NEWS MEDICAL
https://www.news-medical.net/
Eurekalert
https://www.eurekalert.org/
Science News
https://www.sciencedaily.com/
-->