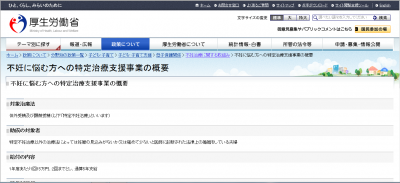新着ニュース30件
2013年8月21日 15:00
不妊治療の公的助成に年齢制限、2016年から実施へ
不妊治療で体外受精を受ける女性患者に対する公費助成に年齢制限をかけることが、ついに現実となった。厚生労働省は19日、体外受精や顕微授精といった不妊治療への公費助成の対象を、42歳までとする新制度を2016年度から実施する方針を示した。
同日開かれた不妊治療への助成の在り方を決める有識者らによる検討会(座長・吉村泰典慶応大教授)で了承された。
現在の制度では、不妊治療への公費助成の対象は、所得制限(夫婦合算で730万円未満)があるものの、年齢制限は設けていない。しかしながら、これまでの研究結果などから、年齢が上がるに連れ、治療の成功率が低下することが分かっており、年齢制限を設けることとなった。
新制度は現在の助成制度を受けている人に不利益が出ないように、周知期間として2年間の移行期間(14年度、15年度)を経て実施することとし、移行期間中は年齢制限を設けないものの、助成回数の上限を現在の10回から、年齢に応じて3~6回とするとした。
16年度から本格的に実施される新制度では公費助成の対象を42歳までとし、43歳以上は対象外とする。また、現在の助成制度では、年間に受けられる助成回数が定められ、制限を設けているが、新制度では年間制限を取り払い、40~42歳は通算3回まで、39歳以下は6回までとする。助成額は現在の制度と同じく、1回15万円(採卵せずに凍結卵を使う場合は7万5000円)を給付する。
卵子のセルフバンク化も視野に
公的費用を投入する助成であるがゆえに、年齢制限を設けることについては理解できるが、仕事や介護などで、出産したくてもできない状況にある女性が存在しているのも事実である。卵子の老化を問題視するのであれば、将来の不妊予防のため、未婚者であっても簡単に卵子凍結ができる制度にするなど、抜本的改革が必要なのだ。卵子のセルフバンク化も早々に取り組まなくてはいけない課題と言える。厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/funin-chiryou.html
-->