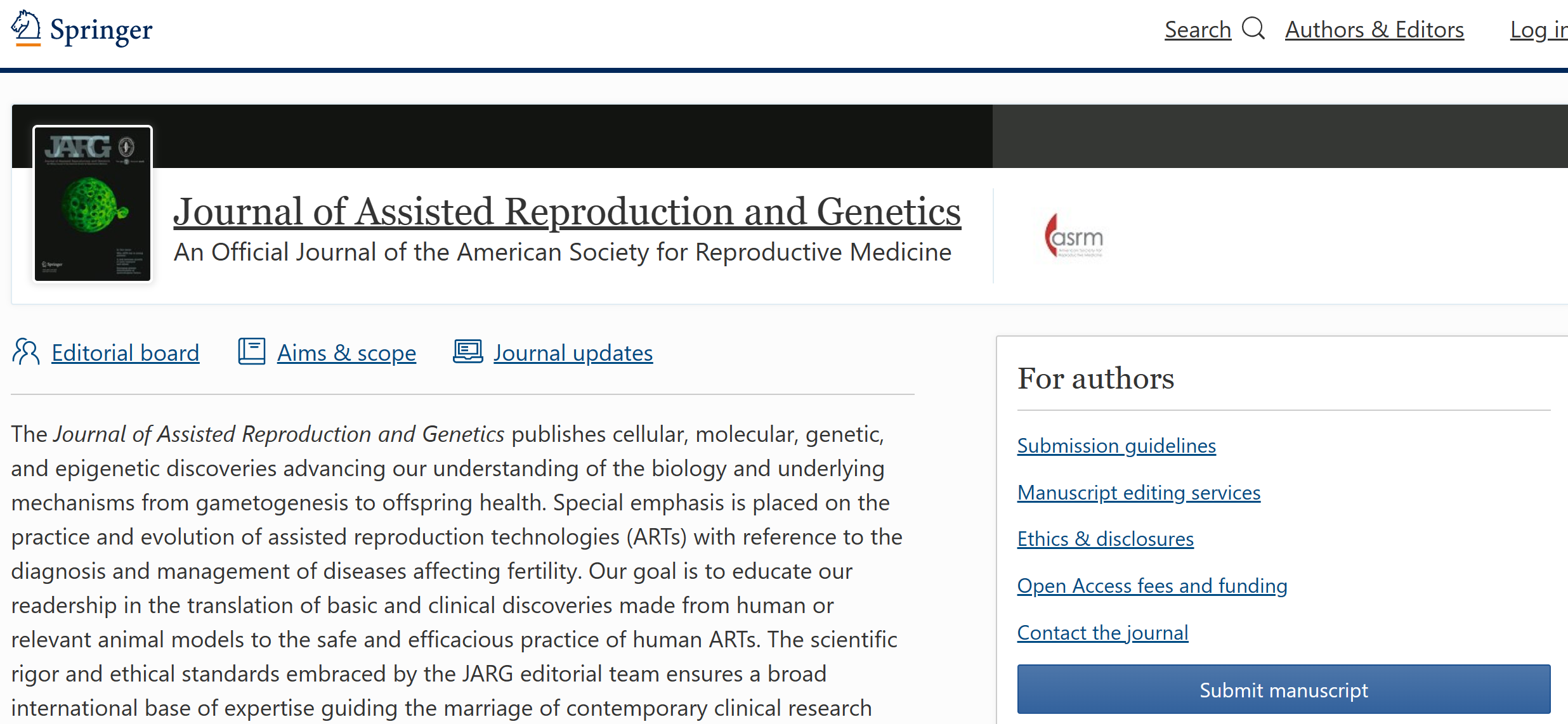新着ニュース30件
2023年1月11日 19:00
卵巣刺激の性腺刺激ホルモンと卵母細胞の質
12月31日、イタリアの研究チームは、「Journal of Assisted Reproduction and Genetics」にて、卵巣刺激おけるゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)投与量は、第二減数分裂中期(MII)の卵母細胞あたりの正倍数性胚盤胞率との関連性はないと発表した。あわせて、ゴナドトロピン投与量と一回目の単一胚移植あたりの出生率において、関連は認められなかった。
卵巣刺激おけるゴナドトロピン投与量による効果
研究チームは、2014年から2018年の期間、細胞質内精子注入と単一胚移植を行った女性(35歳以上、非男性因子不妊、着床前診断1回目)を対象に、卵巣刺激おけるゴナドトロピン投与量による効果を検証した。なお、卵巣刺激には、リコンビナントFSH(遺伝子組み換え型卵胞刺激ホルモン)製剤あるいはhMG(ヒト閉経後ゴナドトロピン)製剤を用いた。
卵巣刺激パターンに基づき4グループ(リコンビナントFSH57個、リコンビナントFSHとLH(黄体形成ホルモン)55個、リコンビナントFSHとhMG112個、hMG127個)に分類し、第二減数分裂中期の卵母細胞あたりの正倍数性胚盤胞率、単一胚移植あたりの出生率を比較した。
リコンビナントFSHグループでは卵巣刺激プロトコルが短く、卵巣刺激ホルモンや黄体ホルモンなど総ゴナドトロピン投与量が最も少ないと報告された。また、胚盤胞の質を調整したうえで4グループを比較したところ、ゴナドトロピン投与量と一回目の単一胚移植あたりの出生率における関連性は認められなかった。
ただし、今回の研究結果は限定的であり、研究チームは、卵巣刺激においてゴナドトロピン投与量と卵母細胞の質に関連性が認められる場合もあると結論付ける。
(画像はJournal of Assisted Reproduction and Geneticsより)
Springer Link
https://link.springer.com/
-->