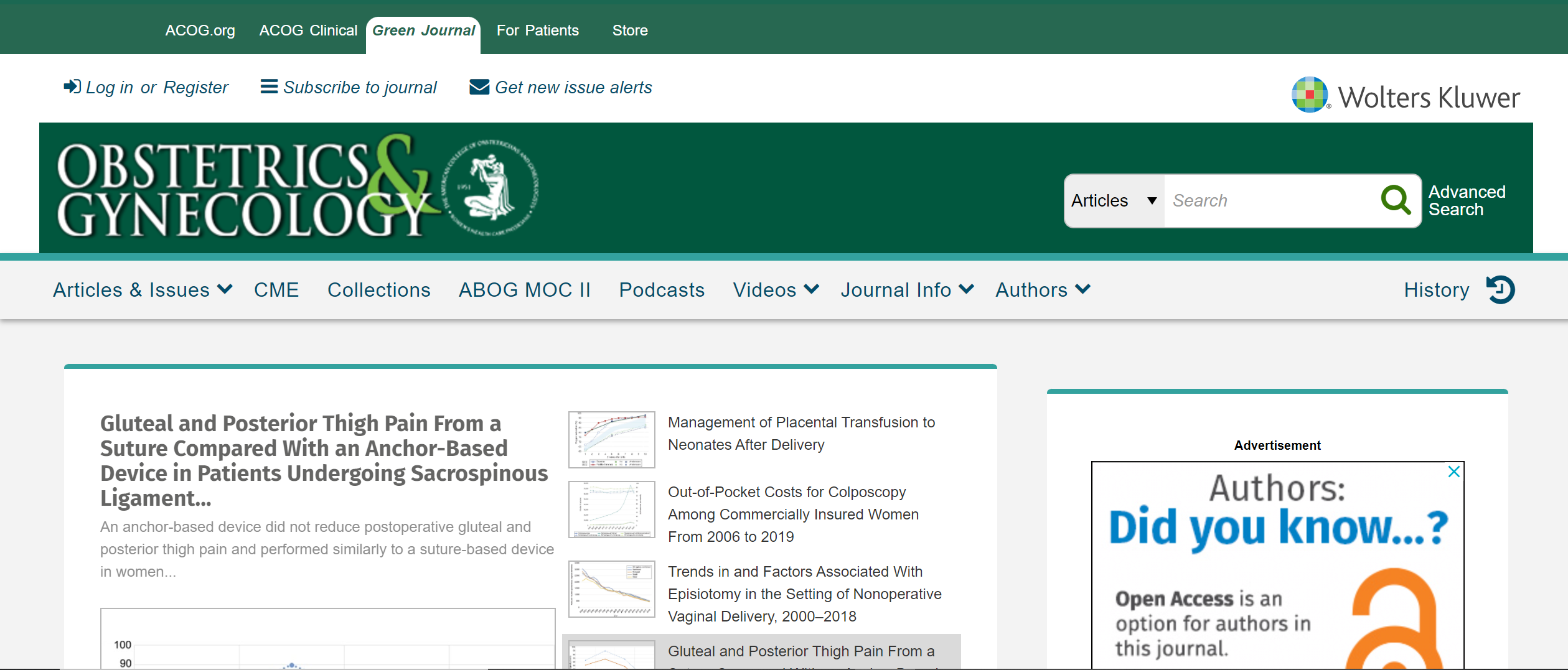新着ニュース30件
2022年1月13日 15:00
低出産体重を誘発する直接要因
1月6日、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(イギリス)とユタ大学(アメリカ)の共同研究チームは、「OBSTETRICS & GYNECOLOGY」にて、生殖補助医療が直接的な要因となり、低出産体重児になる可能性は低いと発表した。これまで、生殖補助医療を介して授かった子供は、自然妊娠と比べて、早産(妊娠37週未満の出産)および低出産体重(出生体重2500g未満)リスクが高まるといわれてきた。
今回、低出産体重の直接起因は生殖補助医療ではなく、家庭環境や両親の特徴による影響が大きいと報告された。
低出産体重児と不妊治療における関係性
研究チームは、「Utah Population Database」を用いて、2009年から2017年の期間、アメリカ・ユタ州にて誕生した新生児248000人を対象にデータ分析を行い、低出産体重児と不妊治療における関係性を検証した。出生体重、在胎期間、低出産体重、早産、在胎不当過小(SGA:在胎期間に比べて小さく誕生した状態)に基づき、自然妊娠および不妊治療による妊娠を比較したところ、人工授精や排卵誘発を含む不妊治療で妊娠した子供は、自然妊娠と比べて早産が10%以上、低出産体重児の割合では9%増えた。
ただし、母親の健康状態(妊娠前のBMI値および血圧)や両親の出産年齢、学歴、経済歴状況に加え、妊娠期間、生殖補助医療、分娩状況に関するデータを加味すると、不妊治療が低出産体重を誘発する可能性は低くなった。
これにより、低出産体重児と不妊治療において、家庭環境、遺伝形質といった両親の特徴が大きく影響していると考えられる。
(画像はOBSTETRICS & GYNECOLOGYより)
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
https://journals.lww.com/
EurekAlert!
https://www.eurekalert.org/news-releases/939274
-->