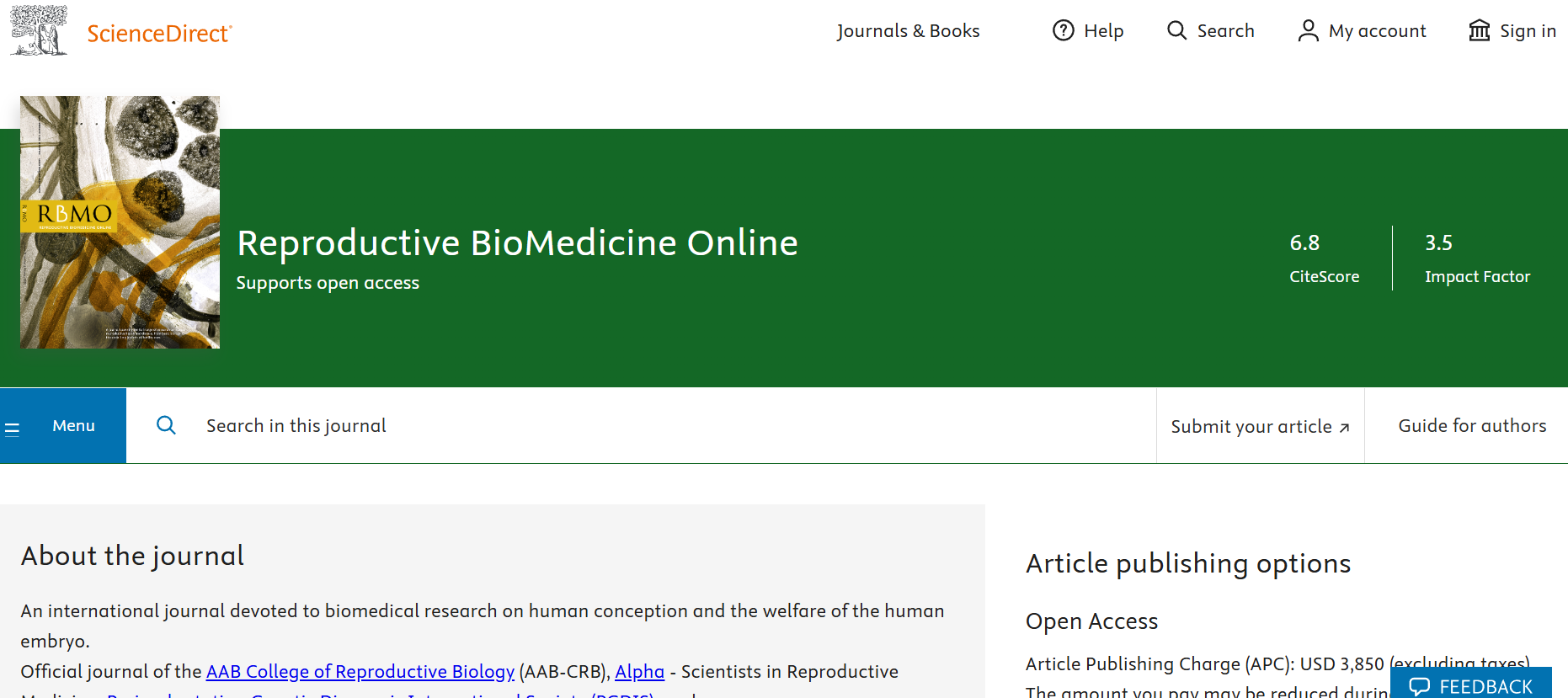新着ニュース30件
2025年10月21日 00:00
内分泌攪乱化学物質曝露による危険性
10月13日、中国の研究チームは、「Reproductive BioMedicine Online」にて、内分泌攪乱化学物質曝露は生殖補助医療の有害転帰と関連性があると示した。卵胞液中の内分泌攪乱化学物質濃度の上昇に伴い、採卵数、成熟卵数、生化学的妊娠率は低下するという。また、内分泌攪乱化学物質曝露による影響は年齢によって変化し、33歳未満において強い関連性が観察された。
内分泌攪乱化学物質曝露が生殖補助医療の結果に及ぼす影響
研究チームは、中国にて生殖補助医療を受ける女性176人を対象に前向きコホート研究を行い、内分泌攪乱化学物質曝露が生殖補助医療の結果に及ぼす影響について検証した。内分泌攪乱化学物質76種類の卵胞液中濃度を測定したところ、15種類の内分泌攪乱化学物質曝露と生殖補助医療の有害転帰において関連性が認められ、特に33歳未満の女性では強い関連性が示された。
例えば、純物質の場合、フタル酸エステル類のモノ(2-エチル-5-カルボキシペンチル)フタレート(MECPP)曝露は、採卵数、成熟卵数、胚盤胞数、良好胚数をはじめ、体外受精・顕微授精の結果に悪影響を及ぼした。
また、混合物の場合では、卵胞液中の内分泌攪乱化学物質濃度の上昇に伴い、採卵数、成熟卵数、生化学的妊娠率は低下した。なかでもフタル酸エステル(PAE)とビスフェノールS(BPS)は、体外受精・顕微授精と生化学的妊娠の有害転帰を引き起こす主な要因として特定された。
なお、卵胞液中の内分泌攪乱化学物質濃度と出生率を含む妊娠結果において関連性は確認されなかった。
(画像はReproductive BioMedicine Onlineより)
ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/
-->